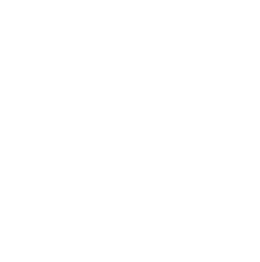総入れ歯とは、すべての歯を失った場合に使用する取り外し式の義歯のことです。上下どちらか、または両方の歯がない場合に装着し、人工の歯と歯ぐきを一体化させた構造になっています。
主な特徴として、歯ぐきや顎の骨に密着させて固定するため、部分入れ歯のように残っている歯にバネをかける必要がありません。 保険適用のものと自費診療のものがあり、使用する素材やフィット感、噛みやすさに違いがあります。
治療期間が比較的短く、手術なしで作れるのが大きなメリットですが、顎の骨が痩せると合わなくなりやすいため、定期的な調整や作り直しが必要になることがあります。